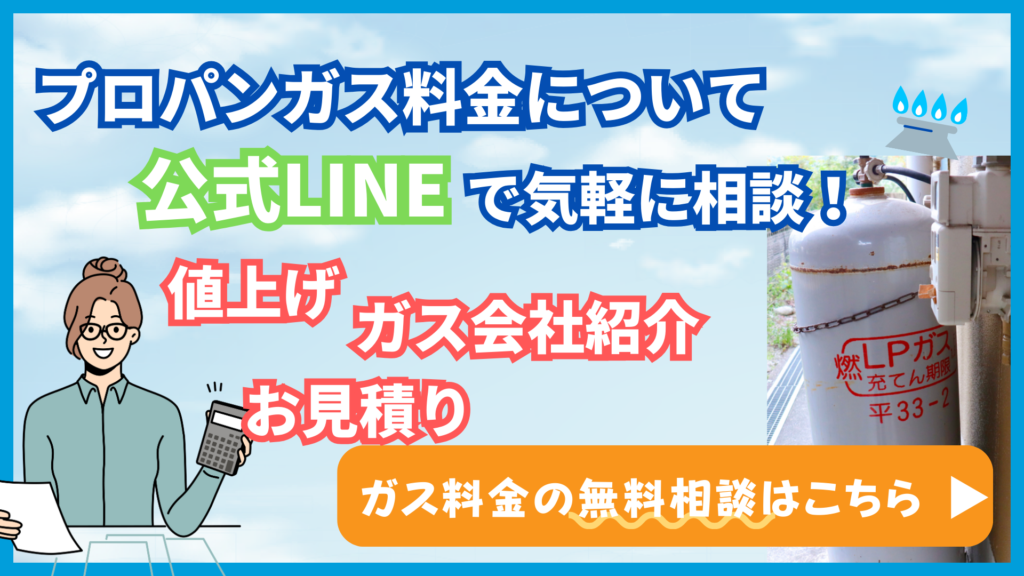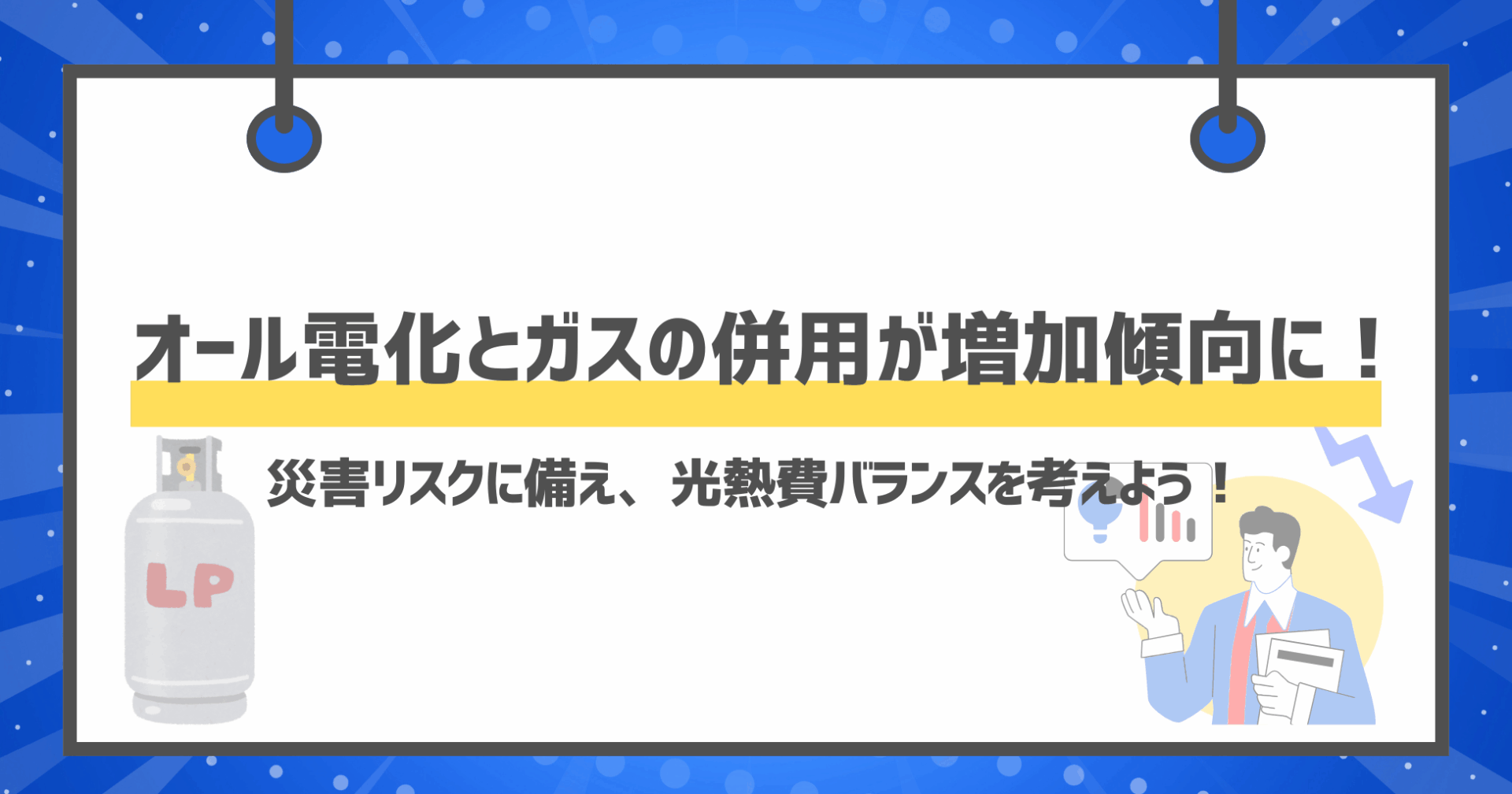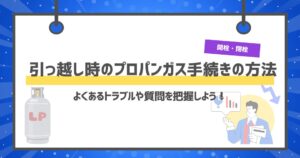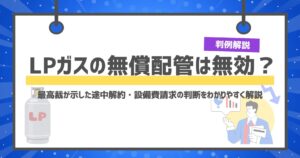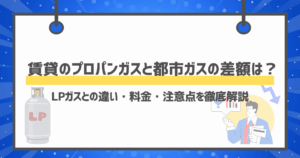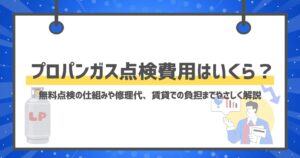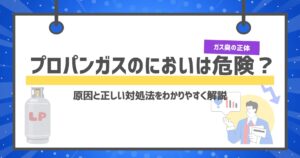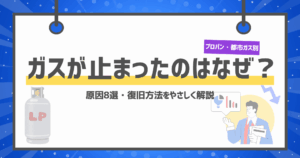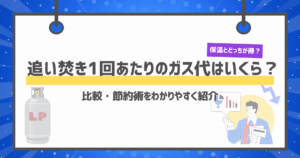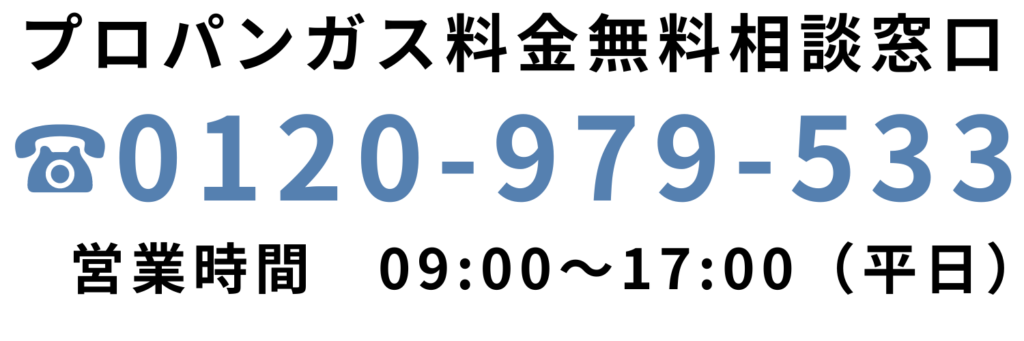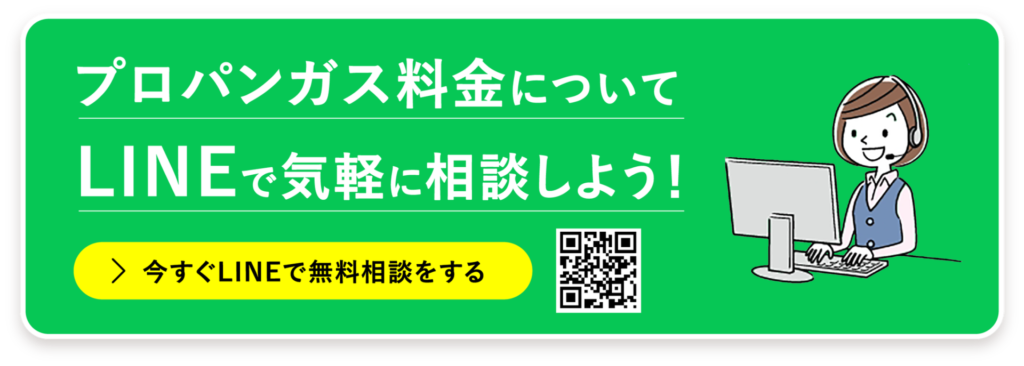近年、災害による大規模停電が相次ぎ、オール電化住宅が抱える弱点にあらためて注目が集まっています。
実際に、停電で暖房も給湯も使えず、近隣の家へお風呂や暖を求めに行かざるを得なかった家庭も少なくありません。
こうした経験から、電気だけに頼らず「ガスも併用しておく」という考え方が全国的に広がりつつあります。
さらに、停電時にも使えるエネファームのような設備の普及も進み、備え方の選択肢は増えています。
この記事では、オール電化とガス併用が注目される理由や防災面でのメリット、費用を考える際のポイントなど、ガス開栓を検討する方が知っておきたい情報を整理してご紹介します。
※年間3000件以上のプロパンガス割高な料金問題を解決してお役に立ちしています
地域別でプロパンガスの適正価格・平均価格をチェック!
近年はオール電化×ガスの併用が増えてる!
近年、地震・台風・竜巻などの自然災害が頻発し、大規模停電が各地で発生しています。
停電が長引いた地域では、給湯や暖房がまったく使えず、近所の家に避難したり、銭湯に通ったりする家庭も多く見られました。
こうした体験をきっかけに「電気だけに頼る生活は不安だ」という声が広がり、オール電化住宅であってもガスを組み合わせる動きが目立つようになっています。
とくに、災害時に強く、停電しても最低限の生活を続けやすい点が評価され、「オール電化×ガス併用」という選択肢に関心が集まっている状況です。
\簡単60秒!無料相談!/
「オール電化×ガス」の併用が増えてる理由
オール電化は長年、安全性やランニングコストの面から支持されてきました。
しかし、近年は電力設備の故障や災害による停電が相次ぎ、「電気だけに頼る暮らしで大丈夫だろうか」と不安を感じる人が増えています。
そこで注目されているのが、ガスと電気を組み合わせる“分散型エネルギー”という考え方です。
IHクッキングヒーターの使いやすさはそのままに、ガス給湯やガスコンロの強みをプラスすることで、日常の快適さと非常時の安心の両方を確保しようとする家庭が増えています。
理由1|災害増加で暮らしの不安が拡大
実際、竜巻で4000件以上の停電が起きた地域では、「お風呂に入れない」「暖房がまったく使えない」といった切実な声が多く聞かれました。
とくにオール電化住宅では、停電と同時に給湯・暖房が一気に止まってしまうため、冬場は生活への打撃が大きくなります。
一方、ガス機器の中には、条件付きではあるものの、電気が止まっても使えるタイプもあり、ガスのほうが先に復旧したケースも報告されています。
こうした実体験を通じて、「電気とガスを併用しておいたほうが安心だ」と考える家庭が増えてきました。
理由2|光熱費の変動と価値観の変化
電気料金の値上がりが続くなか、光熱費を安定させたいという理由でガス併用を選ぶケースも目立ちます。
地域差はあるものの、電気と比べてガスのほうが価格変動が穏やかなことも多く、家計の見通しを立てやすいと感じる人もいます。
また、ガス調理ならではの強い火力や立ち上がりの早さ、ガス給湯のすばやいお湯張りなど、日々の使い勝手を重視してガスを取り入れる家庭も増えています。
「便利さ」「災害への備え」「コストのバランス」といった複数の観点から見て、オール電化ガス併用に切り替える動きが広がっている状況です。
\簡単60秒!無料相談!/
【オール電化のみの場合】停電に対するリスク
オール電化住宅は便利で快適な反面、停電の影響をダイレクトに受けやすい仕組みになっています。
近年は災害だけでなく設備トラブルによる停電も目立ち、「電気が止まったら、我が家の生活はどうなるのか」と心配する人も少なくありません。
電力に大きく依存したライフスタイルを見直そうとする動きも出てきており、停電時に何が起こりうるのかを知っておくことが、これからのエネルギー選びでは重要なポイントになっています。
停電は設備故障でも起きる
停電は地震や台風などの自然災害だけが原因ではありません。
送電線のトラブルや設備の老朽化といった要因でも発生します。
実際に、2018年には送電設備の不具合により広い範囲で停電が起こり、復旧まで数日かかった地域もありました。
このような“思いがけない停電”は前ぶれなく起きるため、オール電化住宅では想定以上の影響が出てしまうこともあります。
季節や時間帯にかかわらず電力供給が止まると、生活インフラが一気に機能しなくなるリスクが高まります。
電力網が複雑になるなか、災害以外の停電にも備えておく必要性が増しているといえるでしょう。
停電時は給湯・暖房・調理ができない
オール電化住宅では、電力が止まると給湯・暖房・調理といった暮らしの基本的な機能が同時に使えなくなってしまいます。
エコキュートは電気制御で動いているため、電源がなければお湯を作れず、タンク内のお湯を使い切れば入浴もできません。
IHクッキングヒーターも停電と同時に停止し、温かい食事を用意することが難しくなります。
さらに暖房をエアコンに頼っている場合、冬の停電では室温が急激に下がり、体調を崩す原因になることも考えられます。
停電が長引けば、暮らし全体の質が大きく落ち込み、家庭の中で安全を確保することさえ難しくなってしまう可能性があるでしょう。
\簡単60秒!無料相談!/
ガスが復旧しやすい理由は?
ガスが比較的早く復旧しやすいのは、電気とは供給の仕組みが異なっているためです。
都市ガスは地中に埋められた配管で供給されており、風で倒れた電柱のような被害は受けにくい構造になっています。
ガス漏れの有無を確認したうえで供給を再開できるため、状況によっては電気より先に使えるようになる場合もあります。
一方、プロパンガス(LPガス)はボンベを各家庭ごとに設置する仕組みです。道路状況が整い配送が再開されれば、ボンベの交換や補充だけで利用できることが多く、戸建て単位で復旧を進められます。
実際の災害現場でも「電気はしばらく使えなかったが、ガスは先に使えるようになった」という事例は少なくありません。
電気の復旧に時間がかかる場面でも、ガスが先に使えることで、日常生活を大きく支えてくれるエネルギーと言えるでしょう。
\簡単60秒!無料相談!/
ガス併用のメリット
ガス併用には、「災害に強い」「調理がしやすい」「暮らし方の選択肢が広がる」など、平常時と非常時のどちらでも活きるメリットがあります。
災害時に使える
ガスは電力系統とは別のルートで供給されるため、停電時にも使える可能性が高いエネルギーです。
とくにプロパンガスはボンベ式の個別供給で、配送体制さえ整えば比較的すぐに利用を再開できる点が大きな強みです。
大規模停電が長引いた地域でも「電気は止まったままだったが、ガスは先に復旧した」という声が複数上がっており、防災の観点からも頼りになる存在といえます。
お湯を沸かしたり、温かい食事を用意できるだけでも、非常時の心細さはかなり和らぎます。
電気の復旧に数日かかる恐れがある地域では、あらかじめガスを併用しておくことで、暮らし方に大きな差が生まれます。
調理性能の高さ
ガスコンロは火力が強く、細かな火加減調整がしやすいことが特徴です。
炒め物のシャキッとした食感や、焼き目の香ばしさなどは、直火ならではの仕上がりになります。
鍋底の温度変化もつかみやすいため、揚げ物や中華料理のように温度管理が重要なメニューにも向いています。
また、電源を必要としないタイプのガスコンロであれば、停電中でも調理が続けられる点も安心材料です。
普段の料理を楽しみつつ、非常時にも頼れる調理手段を確保できるのは、ガス調理ならではの魅力といえるでしょう。
\簡単60秒!無料相談!/
ガス併用のデメリット
ガス併用には多くの良さがある一方で、事前に知っておきたい注意点もあります。
家庭の規模や暮らし方によっては、期待するほど費用対効果が出ないケースもあるため、慎重に検討しましょう。
光熱費が二重になる
電気とガスを併用する場合、それぞれに基本料金がかかります。
そのため、使用量が少ない世帯では「思ったより高くつく」と感じることもあり、結果として光熱費が増える可能性があります。
また、ガスを使う季節とあまり使わない季節で料金の変動が大きくなることもあり、年間を通じた使い方を把握しておかないと節約につながりにくい面もあります。
併用を検討する際は、給湯・調理・暖房の利用状況をあらかじめ整理し、シミュレーションを行っておくと安心です。
設備のメンテナンスコスト
ガス給湯器やガスコンロなどの機器は、安全に使い続けるために定期的な点検や交換が欠かせません。
とくに給湯器は、おおむね10年前後で交換のタイミングを迎えることが多く、その際にはまとまった費用が必要になります。
ガス設備を新たに導入すると、チェックすべき箇所が増えるため、電気設備だけのときに比べて管理の手間が増える点も考慮が必要です。
こうした故障リスクや交換費用も含め、長期的にどの程度のコストがかかるのかをイメージしておかないと、思わぬ出費につながる可能性があります。
プロパンガスの価格差
プロパンガスは自由料金制のため、事業者ごとに価格設定が大きく異なります。
都市ガスより割高なケースも珍しくなく、契約する会社によっては光熱費が増えることもあります。
そのため、オール電化ガス併用へ踏み切る前に、複数社から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較しておくことが大切です。
また、同じプロパンガスでも地域ごとの競争状況によって相場が変わるため、引越し先やエリアの特徴も確認しておきたいポイントです。
適正な価格で利用できる会社を選べば問題ありませんが、情報収集を怠ると不利な条件で契約してしまうおそれがある点には注意が必要です。
\簡単60秒!無料相談!/
オール電化とガスの併用におすすめな「エネファーム」
エネファームは、ガスを使って自宅で発電し、その際に出る熱でお湯もつくる家庭用燃料電池です。
停電時でも条件を満たせば1週間前後の生活を支えられる場合もあり、防災対策として高い関心を集めています。
補助金制度が整ってきたことで導入コストのハードルが下がり、採用する家庭は全国的に増加しました。
静岡ガスの事例では、年間約500件がオール電化からの切り替えで、その多くが「災害への備え」を主な理由としていると報告されています。
また、防災アドバイザーからは「エネファームだけに頼るのではなく、ポータブル電源も組み合わせるとより安心」といったアドバイスもあります。
エネファームでポータブル電源を充電し、冷蔵庫などの大型家電に電気を回す“二段構え”の備えは、実用性の高い対策といえるでしょう。
\簡単60秒!無料相談!/
オール電化とガスの併用が向かない家庭は?
もっとも、オール電化ガス併用がすべての家庭にとってベストというわけではありません。
暮らし方や使用量、家計の優先順位によっては、オール電化のままのほうが合理的なケースもあります。
一人暮らし
一人暮らしでは、給湯量や調理の回数が少ないことが多く、ガスの基本料金が負担になりやすい傾向があります。
自炊をあまりしない、シャワーだけで済ませるといった生活スタイルの場合、ガス併用のメリットを十分に感じにくいかもしれません。
せっかくガス設備を整えても使用頻度が低ければ、コスト面で見合わないこともあります。
光熱費をできるだけ抑えたい単身世帯では、オール電化を維持したほうが、料金管理も含めてシンプルでわかりやすい選択になる場合が多いでしょう。
共働き家庭
共働き世帯は在宅時間が短く、平日日中は家を空けていることがほとんどです。
そのため、ガスを使う機会が限られ、給湯・調理・暖房の利用時間もどうしても短くなりがちです。
ガス併用にしても、基本料金の負担に見合うほど利用しない可能性もあります。
とくに、「まずは光熱費を抑えたい」という考えが強い家庭では、オール電化のシンプルさのほうが合っているケースも少なくないでしょう。
子供がいる家庭は「併用」がおすすめ
一方で、子供がいる家庭ではガス併用のメリットを感じやすくなります。
入浴の回数が多くなるぶん給湯量も増えるため、ガス給湯器のスピード感や安定した湯温は大きな助けになります。
帰宅後すぐにお風呂を準備できることは、子供の体調管理の面でもおすすめです。
また、夜間や早朝の停電に備えてエネルギー源を分散しておけば、突然のトラブルが起きた際も、必要最低限の生活を保ちやすくなります。
調理面でも、ガスの高火力なら短時間で食事を用意できるため、忙しい子育て世帯には心強い存在です。
離乳食の温め直しから、家族分の夕食作りまで効率よく進められ、暮らしのリズムも整えやすくなります。
\簡単60秒!無料相談!/
オール電化とガス併用の判断基準
オール電化ガス併用が自分の家庭に合うかどうかを考える際は、家族の状況・地域の特性・日々の生活パターンを踏まえて総合的に判断することが大切です。
災害リスクの有無
地震や台風、竜巻などの自然災害が多い地域では、電気だけに頼るエネルギー構成はリスクが高くなりがちです。
実際、停電が長引いた地域では「ガスが先に復旧したおかげで何とか生活できた」という事例も多く報告されています。
災害時に「どれくらい早くお湯や食事を確保できるか」は、生活の質に直結します。
停電が起こりやすい地域や災害リスクの高いエリアに住んでいる場合、ガス併用の価値はより高くなると言えるでしょう。
家族構成と使用量
家族の人数が増えるほど、給湯や調理に使うエネルギー量は多くなります。
お風呂の回数が多い家庭や、毎日しっかり料理をする家庭では、ガス給湯器の立ち上がりの早さや、ガスコンロの火力の高さが時短と快適さにつながります。
一方、使用量が少ない家庭では、ガスを併用しても費用面でのメリットを感じにくい場合があります。
家族構成や生活パターン、料理の頻度などを整理したうえで、自宅に合ったエネルギー構成を考えることが重要です。
調理・暖房の快適性
調理の仕上がりや暖房の効き具合にこだわる家庭では、ガス併用のメリットが大きくなります。
ガスの強い火力は料理の幅を広げてくれますし、ガス暖房を選べば部屋が温まるまでの時間を短縮しやすくなります。
とくに冬場でもしっかり暖を取りたい、料理を楽しみたいといったニーズが強い家庭では、ガスは頼りになる存在です。
光熱費をどこまで抑えたいのか、どれくらい快適さを重視したいのかという軸を持って考えると、自分たちに合う答えが見えやすくなります。
\簡単60秒!無料相談!/
オール電化とガス併用に関するよくある質問
Q1.切替のタイミングは?
給湯器・エコキュート・IHコンロなどが寿命を迎えるタイミングが、ガス併用へ切り替えやすい時期です。
これらの設備はおおむね10〜15年ほどで更新が必要になるため、その入れ替えのタイミングで併用に移行すれば、工事もまとめやすくなります。
防災面を強化したい場合は、計画的に前倒しで検討するのも一つの方法です。
自治体の補助金が使える場合もあるため、事前に情報を確認しておくと導入コストを抑えられる可能性があります。
Q2.電気代高騰対策になる?
ガス併用によって電気の使用量を減らせれば、電気料金の高騰対策として一定の効果が期待できます。
特に給湯のウエイトが大きい家庭では、ガス給湯器のほうが効率よく、結果として電気代の負担を軽くできるケースもあります。
ただし、ガスの使用量が増える点は避けられないため、光熱費全体をトータルで見ることが欠かせません。
電気代とガス代の両方を試算したうえで、最終的に家計にとってプラスになるかを判断することが大切です。
Q3.プロパンガスは高い?
プロパンガスは都市ガスとは違い自由料金制のため、事業者によって料金に差があります。
たしかに高めの価格設定をしている会社もありますが、適正価格で提供している事業者を選べば、必要以上に負担が増えるとは限りません。
ポイントは、複数社を比較し、料金表の分かりやすさやサポート体制を確認してから契約することです。
また、地域によって相場が異なるため、引越しの際は新しいエリアの状況をチェックしておくと安心です。
適切な事業者を選べれば、プロパンガスもオール電化 ガス併用の有力な選択肢になります。
\簡単60秒!無料相談!/
まとめ
災害や停電が増えている今、電気とガスを組み合わせて備えておくという考え方は、着実に広がっています。
電気が使えない状況でも、お湯を沸かしたり温かい食事を作れたりする安心感は、日々の暮らしに大きな余裕をもたらすものです。
一方で、光熱費や設備の管理といった面では、各家庭でしっかりと検討しておきたいポイントもあります。エネファームをはじめ、ガスを活かした設備や支援制度も利用しやすくなってきました。
自分たちの生活スタイルに目を向けながら、オール電化 ガス併用を含めたエネルギーの使い方を見直してみることで、より安心で快適な住まいづくりにつながっていくでしょう。